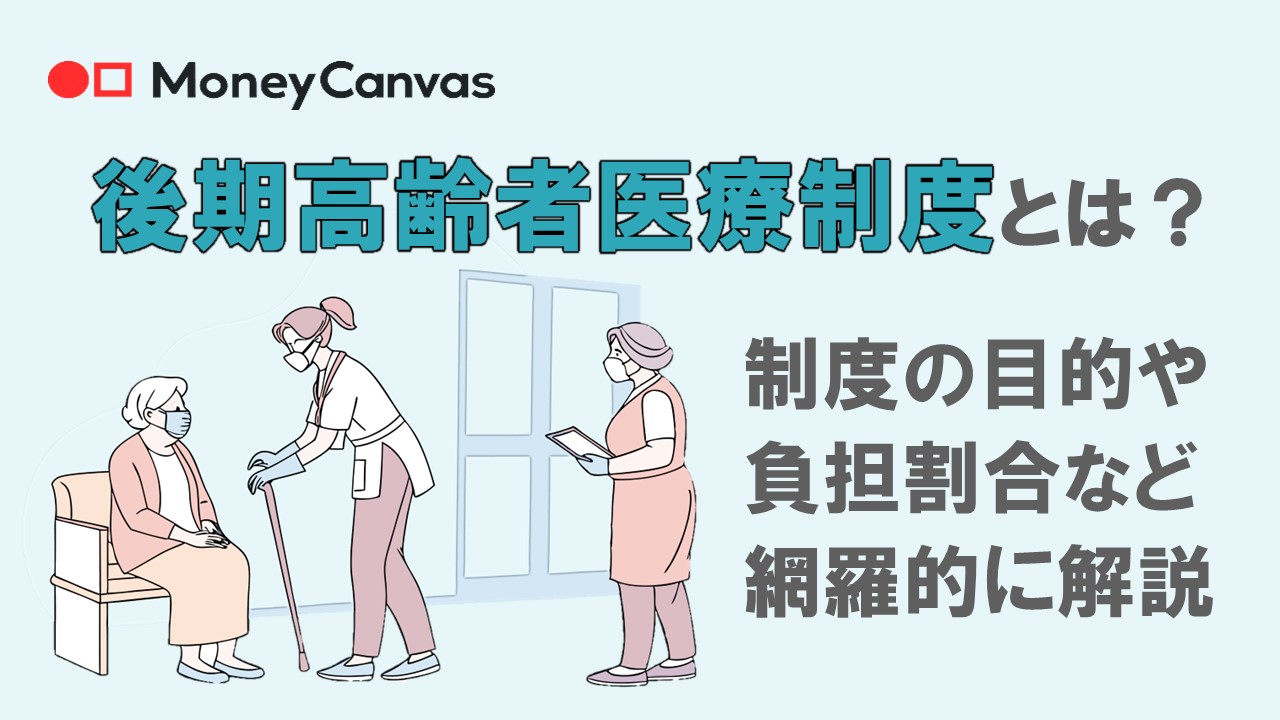
後期高齢者医療制度とは?制度の目的や負担割合など網羅的に解説
日本は世界でも有数のスピードで高齢化が進み、医療費の伸びと財源確保の両立が大きな政策課題になっています。
こうした背景で設計されたのが、75歳以上(一定の障害がある65~74歳を含む)を対象とする「後期高齢者医療制度」です。
保険料・公費・現役世代からの支援金という三本柱で費用を支える仕組みにより、高齢者が安心して必要な医療を受けられる体制を守りつつ、世代間の負担の均衡を図ります。
運営主体は都道府県単位の「後期高齢者医療広域連合」で、各市区町村が窓口業務を担います。
制度の構造と運用の要点を押さえておくことは、老後の医療費・生活費の見通しを立てるうえで役に立つでしょう。
後期高齢者医療制度とは?
後期高齢者医療制度は2008年に創設された公的医療保険制度です。
給付費(窓口自己負担を除く)の概ね公費約5割+支援金約4割+被保険者保険料約1割という財源構成を採っています。*1
近年もこの基本構造は維持され、広域連合が財政を一元管理し、自治体と連携して給付・保険料賦課・資格管理を行うことになっています。
なお、創設当初の制度資料では現役並み所得者については公費負担の対象外とされた経緯が示されており、負担能力に応じた設計思想が組み込まれてきたことが分かります。*1
制度の概要
財源の柱である保険料は、各広域連合が「均等割(定額)」と「所得割(所得比例)」を組み合わせて決定します。
具体的には、 加入者全員が等しく負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて算出される「所得割額」の合計が、年間の保険料となります。*1
所得割の計算基礎となるのは、前年の総所得金額等から基礎控除(合計所得金額2,400万円以下の場合43万円)を差し引いた金額です。*2
保険料率は2年ごとに見直されるため、定期的に自身の保険料額を確認することが大切です。
直近の取りまとめでは、被保険者1人当たりの平均保険料(月額)7,082円(令和6年度)→7,192円(令和7年度見込み)と公表されており、地域差はあるものの、料率や軽減措置の見直しを通じて制度の安定運営が図られています。*3
低所得世帯向けには均等割の7割・5割・2割軽減などの法定軽減が用意され、負担の過重を抑制しています。*1
納付方法は、原則として年金からの特別徴収(天引き)ですが、年金受給額が一定未満の場合や「介護保険料と合算した天引き額が年金の1/2超」の場合などは普通徴収(口座振替・納付書)に切り替わります。*4
基準としては「年金年額18万円以上が特別徴収の対象」などが示され、自治体の運用に沿って自動的に切替が行われます。
希望すれば、申請により特別徴収から口座振替へ変更することも可能です。
ただし、保険料の納付実績などによっては変更が認められない場合もあるため、納付方法の変更可否や時期は、加入先の広域連合・市区町村で必ず確認しましょう。*4
対象者と加入条件
主な対象は75歳以上で、65~74歳でも一定の障害認定を受けた方は加入できます。
75歳到達に伴い、原則として国民健康保険や被用者保険から自動切替されるため、大がかりな手続きは不要です。
75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた健康保険の資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
新しい保険証(後期高齢者医療被保険者証)は、誕生日の前月までに市区町村から郵送されるのが一般的です。*1
障害認定の範囲(例:障害年金1・2級、身体障害者手帳1~3級など)は広域連合が示す基準に沿って判断されるため、該当の可能性がある場合は自治体窓口で要件をご確認ください。*1
後期高齢者医療制度の目的
制度の目的は、主に以下の3つです。*1
- 高齢者の適切な医療アクセスの確保
- 世代間・世代内の公平な費用分担
- 制度の持続可能性の確保
日本の国民皆保険制度は、 現役世代が納める保険料が高齢者世代の医療費を支える構造になっています。
しかし、少子高齢化が急速に進んだことで、一人の高齢者を支える現役世代の人数が減少し、従来の仕組みでは現役世代の負担が過大になるという課題に直面しました。
そこで、高齢者自身も保険料を負担し、さらに公費を投入することで、世代間の負担を明確化し、社会全体で支える仕組みとしてこの制度が導入されたのです。*1
実際、直近の財政状況では被保険者数1,989万人(前年度+64万人)、単年度収入17.6兆円・支出17.7兆円と規模が拡大する一方、収納率は99.51%と高水準を維持しており、広域連合単位での安定運営が確認できます。
今後も高齢化の進展で給付費の増勢が見込まれるため、財源の多支柱化と負担能力に応じた仕組みが不可欠です。*5
高齢者の医療費の負担割合はどのくらい?
窓口負担は原則1割で、一定以上の所得がある方は2割、現役並み所得者は3割です。*6
3割負担となる「現役並み所得者」とは、住民税の課税所得が145万円以上の方を指します。
収入合計が単身世帯で約383万円未満、二人以上の世帯で約520万円未満の場合は、申請により1割または2割負担に変更できる場合があります。*6 *7
また、2022年10月から導入された2割負担の対象は、課税所得が28万円以上かつ年収が単身で200万円以上(複数世帯で合計320万円以上)の方です。
所得判定により1割→2割となる層が導入され、外来の負担増を月3,000円までに抑える配慮措置(~2025年9月診療分)が設けられています。*7
さらに、高額療養費制度により、年齢・所得区分ごとに月ごとの自己負担上限が設定されています。
例えば、一般所得(1割・2割負担)の方の外来上限額は個人単位で月18,000円(年間上限144,000円)です。
入院を含む世帯全体の上限額は、2025年8月~2026年7月は月60,600円(それ以前は57,600円)となります。
2026年8月以降は外来上限の段階的引き上げが予定されています。*8
この上限を超えた分は、後日申請することで払い戻されます。
事前に「限度額適用認定証」の交付を受けて医療機関に提示すれば、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることも可能です(住民税非課税世帯などが対象)。*9
個人ごとの外来と世帯合算の上限が別々に定められている点、多数回該当(過去12か月に3回以上上限に達すると上限が下がる)がある点を理解しておくと、急な入院や高額治療でも家計の想定が立てやすくなります。
判定に使う「課税所得」や外来・入院の扱いは資料で明確に示されているので、年1回は最新の上限表を確認しましょう。*8
後期高齢者医療制度についてよくある質問
後期高齢者医療は、デジタル化や負担見直しなどの制度更新が続く分野です。
ここでは、紙の保険証の廃止時期、マイナ保険証が手元にない場合の受診方法、マイナ保険証の主なメリットを整理します。
紙の保険証は25年7月で有効期限が切れる?
政府方針により 2024年12月2日に現行の保険証の新規発行が停止され、有効期限内(最長2025年12月1日まで)は利用可とされています。*11
後期高齢者医療保険の被保険者証の有効期限は2025年7月31日となる旨の注意書きも出ています。
以後は基本的にマイナ保険証を用いますが、保険資格の変更が生じた場合でも、移行期の受診手段が確保されるよう段取りが示されています。
スケジュールや手続きは随時更新されるため、必ず最新情報で確認してください。*10 *11
マイナ保険証を持っていない場合はどうすればいい?
資格確認書が申請不要・無償で交付され、当面はマイナ保険証がなくても受診できます。*12
とくに75歳以上(および一定の障害がある65~74歳)の被保険者については、2026年7月末までの暫定措置として一律交付される運用が示されました。
有効期限や送付時期は保険者で異なるため、加入先からの通知に必ず目を通しましょう。*11 *12
マイナ保険証を発行するメリットは?
マイナ保険証には、主に以下のような実務面の利点があります。*10
- 資格確認や負担割合の判定が迅速になる
- 薬剤情報や健診結果等の連携で重複投薬・検査の回避に寄与する
- 保険証の更新手続きが不要になる
特に2つ目のメリットは、複数の医療機関を受診している高齢者にとって大きな安心材料です。
医師や薬剤師が過去の処方薬や特定健診の情報を正確に把握できるため、より安全で質の高い医療につながるでしょう。*10
オンライン資格確認の普及により、高額療養費の限度額情報の連携も進み、窓口支払いの一時負担を抑えやすくなります。
カードの扱いが難しい方には前述の資格確認書という代替手段が用意され、移行期でも受診機会を損なわない配慮がとられています。*10
将来の医療費に備えるための実践ポイント
これまでの要点を、将来に備えるための実践的なポイントとして整理しましょう。
まず、ご自身の保険料額と納付方法を把握しておくことが基本です。
保険料は全国平均で月額7,192円(令和7年度見込み)が目安となります。
納付書が届くか、年金から天引きされるかを確認し、希望があれば口座振替に変更することも検討しましょう。
次に、窓口での自己負担を抑える「高額療養費制度」を理解しておくことが大切です。
医療費には所得に応じた上限額が設定されており、今後の制度改正で上限額が見直される予定です。
ご自身の区分の上限額を把握しておくと、万が一の入院や治療の際にも落ち着いて対応できます。
実際に医療機関にかかる際は、以下の点を準備しておくとスムーズです。
- 負担割合(1・2・3割)の通知や高齢受給者証の確認
- マイナ保険証の利用登録(限度額情報の連携に有利)
- 資格確認書の保管(紛失時は再交付手続き)
- 高額療養費の申請要否と入院前の確認
特に、住民税非課税世帯の方などは、窓口での支払いを上限額までに抑える「限度額適用認定証」の事前申請が必要な場合があります。
制度は今後も定期的に見直されます。厚生労働省やお住まいの自治体からのお知らせに関心を持ち、 常に最新の情報を確認する習慣が、将来の医療費への不安を和らげてくれるでしょう。
本コラム執筆時点における情報に基づいて作成しておりますので、最新情報との乖離にご注意ください
出典
*1 厚生労働省「高齢者医療制度の概要等について」
*2 東京都主税局「個人住民税」
*3 厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について」
*4 厚生労働省「介護、国保、後期高齢における保険料の特別徴収について」
*5 厚生労働省「令和5年度後期高齢者医療制度(後期高齢者医療広域連合)の財政状況について」
*6 厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」
*7 厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」
*8 厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」
*9 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
*10 厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
*11 厚生労働省「健康保険証は12月2日以降新たに発行されなくなりました」
*12 デジタル庁「資格確認書(マイナ保険証以外の受診方法)」


