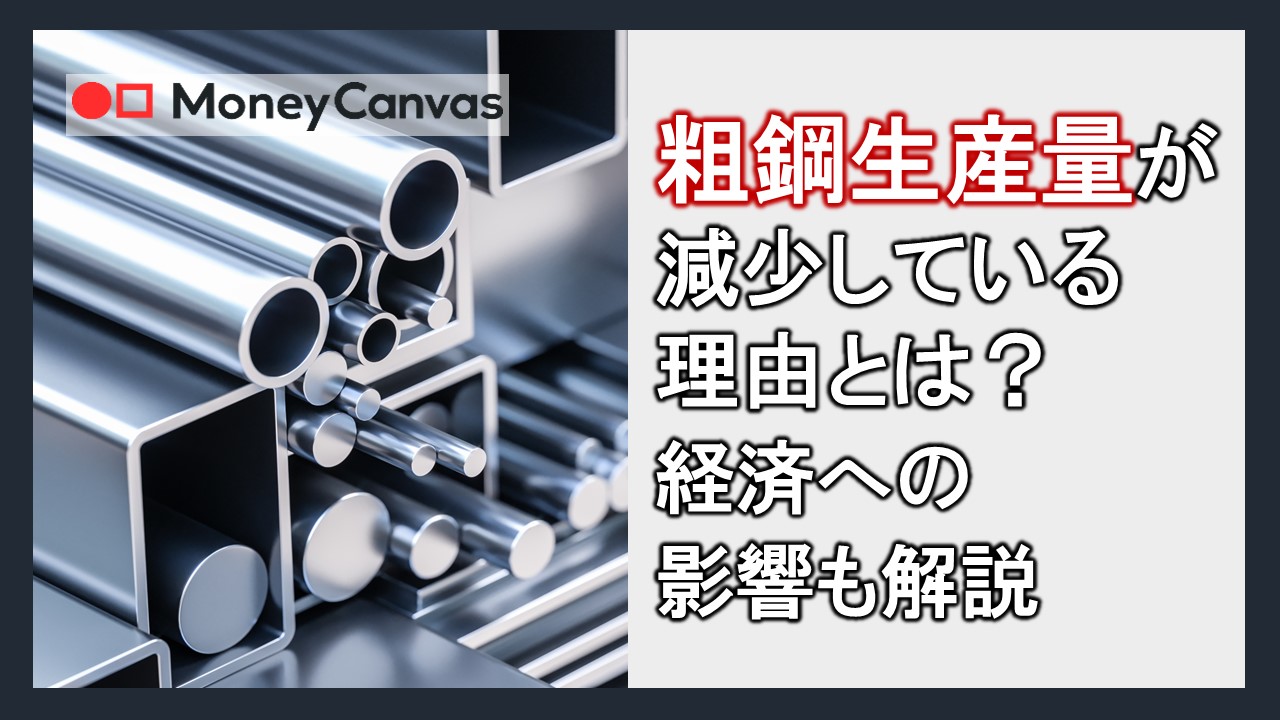
粗鋼生産量が減少している理由とは?経済への影響も解説
粗鋼生産量は国の工業生産を支える重要な指標です。
しかし、日本では2022年ごろから生産量の減少が続き、2024年も前年割れとなる状況です。
背景には国際的な需要の低迷や原料高、脱炭素政策の強化などが絡み合っており、製鉄業界だけでなく建設や輸送、資源開発など広範な分野に影響を及ぼしています。
本記事では粗鋼生産量の減少要因を整理し、その結果起こり得る影響や株式市場への波及までを解説します。
将来の資産形成を考える読者の方にとって、国内外の鉄鋼需要の動向を理解することは投資判断の一助となるでしょう。
粗鋼生産量が減少している原因
粗鋼生産量が減る背景には複数の要因が絡み合っています。
ここでは中国を中心とした国際市場の変化、国内需要の落ち込み、コスト高、脱炭素政策の4点から整理していきましょう。
中国の輸出圧力
世界最大の鉄鋼生産国である中国では、不動産市場の不振や国内需要の低迷を背景に鉄鋼製品の輸出が増加しています。
中国政府は2021年以降、鉄鋼業界に対して二酸化炭素排出量削減を求める政策を打ち出し、高炉の新設や粗鋼生産量を抑制する方針を示しました。*1
この政策により2020年に10億6500万トンだった中国の粗鋼生産量は2024年に10億500万トンまで減少し、同時に海外輸出が大幅に伸びる結果となりました。
国内需要が伸び悩む中、中国メーカーは余剰分を海外市場に放出しており、2024年の鋼材輸出は前年比で約1割増え、1億1100万トン超と2015年以来の高水準となっています。*2
価格競争力の高い中国製鋼材が市場に溢れた結果、日本を含む他国の鉄鋼メーカーは価格低下に直面し、生産調整や減産を余儀なくされている状況です。
加えて、中国政府は高炉中心の生産を抑制し電炉比率を引き上げる方針を掲げており、2025年までに電炉比率を15%へ高める目標を示しています。*1
こうした政策の影響で世界全体の鋼材の供給構造が変化し、他国の高炉稼働率に下押し圧力がかかっているといえるでしょう。
国内の建設・不動産市場の需要の減少
日本国内では住宅着工件数や不動産開発が減少し、建設向け鋼材需要が縮小しています。
国土交通省の統計によると、2024年の新設住宅着工戸数は79万2098戸で前年比3.4%減と2年連続で前年を下回りました。
持ち家は21万8132戸で2.8%減、分譲住宅は22万5309戸で8.5%減となり、全体的に住宅需要が落ち込んでいることが分かります。*3
さらに、この統計では注文住宅の着工戸数が32か月連続、分譲住宅は21か月連続で前年割れを記録しており、建設需要低迷が長期化していることが示されています。*3
住宅やビルの建設に使われる鋼材は粗鋼需要の大きな部分を占めます。
住宅着工の減少や不動産開発の停滞によって鉄筋や鋼板の需要が縮小し、日本の粗鋼生産量の減少に直接的な影響を及ぼしているのです。
建設以外でも、製造業の設備投資抑制や公共投資の減少が重なり、国内の鋼材需要全体が弱含みとなっています。
原料価格の高騰と輸送コストの上昇
鉄鋼の主原料である鉄鉱石や石炭は、国際市況の影響を受けやすい資源です。
日本特殊鋼倶楽部の機関誌では、2003年以降鉄鉱石価格が大幅に上昇し、現時点でも1トン当たり100ドルを超える水準にあると指摘しています。*4
中国の需要増加や環境規制強化に伴い、高品質の塊鉱やペレットへの需要が高まり、それに伴いプレミアムも上昇している状況です。
また石炭や電力などのエネルギー価格も高騰し、工場の操業コストを押し上げています。
日本の製鉄業界では円安による輸入品の値上がりも負担となり、コストの上昇分を販売価格に転嫁しきれない状況が続いています。*4
物流面でも課題は深刻化しています。
2024年問題(物流業界の労働時間規制強化)によって輸送コストの長期的な上昇が懸念されており、鉄鋼製品の配送コストや原料輸入コストに直接影響を及ぼすでしょう。*4
加えて、世界的な海上輸送費の高騰や円安が重なり、鉄鉱石やスクラップの輸入費用が増大。これら原料・エネルギー・輸送コストの上昇は採算を圧迫し、一部の高炉では休止や減産が進んでいます。
脱炭素政策による生産制限
地球温暖化防止に向けた脱炭素政策は鉄鋼業界にも大きな影響を与えています。
日本政府は2030年度のCO2排出削減目標を2013年度比46%減と設定しており、製鉄業界に対して省エネ設備の導入や高炉の休止を求めているのです。
世界的に見ると、中国政府は粗鋼生産量の「ゼロ成長」を掲げ、新規高炉建設を制限し老朽高炉の閉鎖やスクラップ電炉への転換を推進しています。*1
こうした政策の下、高炉の稼働率は抑えられ、新規投資も慎重にならざるを得ません。
さらにEUは2026年に炭素国境調整措置(CBAM)を本格導入し、輸入鋼材にも炭素コストを課す予定です。
日本メーカーにとっても温室効果ガス排出量の少ない「グリーン鋼材」への対応が急務となり、設備投資や研究開発コストは増大しています。
脱炭素政策の強化は長期的に生産・販売の構造変化を促し、短期的には粗鋼生産量を抑制する要因となっているといえます。
粗鋼生産量の減少によって起こること
生産量の減少は、需給バランスや設備稼働にさまざまな影響を及ぼすと考えられます。
ここでは在庫動向と稼働率への影響を見ていきましょう。
鋼材の在庫が増える
需要が低迷する一方で生産調整のスピードが追いつかない場合、倉庫や港湾に鋼材在庫が積み上がることがあります。
日本鉄鋼連盟の「鉄鋼需給の動き」によると、2024年11月の粗鋼生産量は前年同月比3.1%減の689万トンで9カ月連続の減少となりました。
同資料では普通鋼在庫(国内流通在庫)が10月末時点で511万トンと、前月より減少したものの在庫率は163.2%と高水準にあると報告されています。
需要減少による出荷鈍化が続けば、在庫調整圧力が高まり、価格下落を招く恐れがあるでしょう。*5
過剰在庫が続くと製品価格が下押しされ、鉄鋼メーカーだけでなく流通業者の収益も圧迫することになります。
一般に在庫率が160%を超えると供給過剰感が強く、値引き販売や減産による調整が行われやすくなります。
これが粗鋼生産量のさらなる縮小を招く悪循環を生みかねません。
鉄鋼メーカーの稼働率低下
粗鋼生産量の減少は工場の稼働率低下につながります。
高炉は一度稼働を止めると再稼働に時間とコストがかかるため、減産が必要になれば稼働率を下げたり一部高炉を休止したりするなどの対応が求められます。
日本鉄鋼連盟の資料では、普通鋼の生産量が前年同月比7.9%減となっており、国内出荷量も減少傾向が続いています。*5
稼働率が低下すれば固定費の負担が相対的に重くなり、損益分岐点が上昇することになります。
特に高炉メーカーは大規模な設備を抱えているため、稼働率の低下がそのまま利益率の低下につながるのです。
このため、メーカー各社は設備休止や海外拠点の拡充、電炉へのシフトなど様々な施策で収益性を維持しようとしています。
長期的には設備再編が進み、生産能力の削減と電炉への投資が併行して進む可能性があります。
粗鋼生産量の減少が株価に与える影響は?
粗鋼生産量の減少は鉄鋼メーカーの業績予想や株価にどのような影響を及ぼすのでしょうか。
ここでは短期的な下振れリスクと中長期的な成長材料の両面から考えていきましょう。
業績予想の下方修正による株価の下振れリスク
粗鋼需要が減少し、原料高や脱炭素への投資負担が増えると、メーカー各社は業績予想を引き下げる可能性があります。
世界鉄鋼協会は2024年の世界粗鋼需要見通しを4月時点の1.7%増から0.9%減の17億5000万トンへ下方修正し、世界の製造業が逆風に苦しんでいると指摘しています。*6
主要国の需要減少と価格下落を背景に、日本の高炉メーカーも2025年度の連結業績予想を慎重に見直しています。
このように業績予想が引き下げられる局面では投資家の警戒感が高まり、株価が一時的に下押しされるリスクがあるといえるでしょう。
短期的には減益決算や配当の減額観測が嫌気される可能性があるため、株式投資では業績のボトムを見極めることが重要になります。
グリーン鋼材市場の成長が見込まれる
一方で脱炭素化の潮流は新たなビジネスチャンスも生んでいます。
グリーン水素を利用する直接還元鉄(DRI)やスクラップ電炉で生産された「グリーン鋼材」の需要は、環境規制の強化やサプライチェーンの脱炭素要請を背景に拡大すると予想されています。
国際エネルギー機関(IEA)は2030年までにグリーン鋼材市場が世界粗鋼生産の5%程度に相当する1億トン規模に達すると予測しています。*7
日本の大手鉄鋼メーカーも脱炭素技術への投資を進めており、高炉由来のCO2排出を大幅に削減するCOURSE50プロジェクトや水素還元鉄の試験設備を稼働させています。
こうした取り組みが実用化されれば、環境規制への対応だけでなく新たな収益源となり、株価の下支え要因になり得ます。
中長期的にはグリーン鋼材の供給力をいち早く確保した企業が市場で優位性を持つことも期待されるため、脱炭素戦略の進捗が投資判断の重要な尺度となるでしょう。
将来展望と投資家への示唆
粗鋼生産量の減少は、中国の輸出拡大や国内需要の縮小、原料・物流コストの高騰、脱炭素政策という複数の要因が絡み合って引き起こされています。
短期的には在庫増や稼働率低下を通じて企業業績や株価を下押しするリスクがあり、メーカー各社は生産調整や事業再編を進めざるを得ません。
一方で、脱炭素化への対応を迅速に進めることで、グリーン鋼材という新市場への参入機会が広がります。
投資家にとっては、粗鋼需要の変動リスクとともに各社の脱炭素戦略や財務健全性を見極めることが重要といえます。
価格競争力や輸出比率に左右される短期的な業績だけでなく、環境投資の進捗やグリーン鋼材への転換能力が中長期的な企業価値のカギを握るでしょう。
日本の鉄鋼業は自動車・建設・機械など幅広い産業を支える基幹産業です。粗鋼生産量の減少が示す構造変化を正確に理解し、将来のビジネスチャンスとリスクの両面を意識した投資判断が求められています。
本コラム執筆時点における情報に基づいて作成しておりますので、最新情報との乖離にご注意ください。
本コラムの内容は、特定の金融商品やサービスを推奨あるいは勧誘を目的とするものではありません。
最終的な投資判断、金融商品のご選択に際しては、お客さまご自身の判断でお取り組みをお願いいたします。
出典
*1 NPI 中曽根康弘世界平和研究所「中国、インドの鉄鋼業における低、脱炭素化の取組み」
*2 Reuters「中国粗鋼生産、24年は5年ぶり低水準 不動産市場危機が需要圧迫」
*3 国土交通省「建築着工統計調査報告」
*4 特殊鋼「最近の特殊鋼原料事情」
*5 日本鉄鋼連盟「鉄鋼需給の動き」
*6 Reuters「世界の鉄鋼需要、24年1.7%減に下方修正 製造業など低迷=業界団体」
*7 経済産業省 資源エネルギー庁「鉄鋼業の脱炭素化に向けた世界の取り組み(前編)~「グリーンスチール」とは何か?」


