
投資信託のコストの中身を知っておこう!
投資信託を始めようと思っている方、または既に投資信託を始めている方の中にも、投資信託はコストが重要だと聞いた方は多いと思います。
とくに「信託報酬」は、投資信託の保有期間中、投資家が負担し続けるコストなので、その内容についてはしっかり理解しておきたいところです。今回は、「信託報酬」に代表される投資信託のコストに着目してみたいと思います。
- 投資をする上ではコストに注意
- 投資信託のおもなコスト
- 信託報酬の内容は?
- 信託報酬はいつ支払うのか
- 信託報酬などコストだけで投資信託を見てしまうと失敗する?!
- 投資信託のタイプと信託報酬の関係
- つみたてNISAの信託報酬はどのくらい?
- 商品の仕組みやコストをしっかり理解しよう
投資をする上ではコストに注意

一般的に株式や債券、投資信託など金融商品に投資する場合は、相応のコストがかかります。とくに、投資信託の場合は、購入時だけでなく保有期間中もコストを負担しているという点は、長期投資という観点からも注意が必要でしょう。
投資信託のコストは、どこを見ればわかるのかというと、投資信託を購入する際、投資家が必ず目を通す「投資信託説明書(交付目論見書)」(以下「交付目論見書」)に記載されています。この「交付目論見書」のファンドの費用が示されたページに、投資家が負担するすべてのコストが説明されています(以下、投資信託のことを「ファンド」と呼ぶ場合もあります)。
つまり、投資家は投資信託の購入前に、ファンドの「交付目論見書」に目を通すことによって、ファンドによるコストの水準の違いを比較することができるのです。
株式や投資信託をはじめとした金融商品にかかるコストは、一般的に投資家が得る最終的なリターンに影響を与えます。投資信託の場合であれば、信託報酬などのコストが投資信託そのものの運用パフォーマンスに影響を与えているということは覚えておきましょう。
投資信託は、長期投資を前提に購入される方も多いと思いますが、そうすると長期にわたって、コストの影響を受けることになります。つまり、自ずと投資家の負担額も増えていくことになります。
そのため、投資信託を選ぶ際には、運用パフォーマンスの実績と同様、コストについてもしっかりと確認しておく必要があります。
投資信託の仕組み
投資信託のコストを説明する前に、投資信託の仕組みをおさらいしておきましょう。
投資信託には、通常、3つの会社が関係しています。
まず、投資信託の運用会社で、これを委託会社といいます。金融商品としての投資信託を企画・開発し、投資信託の運用を行うファンド・マネージャーという専門家も在籍していて、投資信託に関わる会社の中では、最も重要な役割を担っていると言えます。
次に、投資家と委託会社をつなぐ銀行や証券会社など、販売会社があります。販売会社は、投資家の口座を管理し、法定書類などを投資家に交付するなどの役割を担っています。
そして最後に、投資家の資金をまとめて信託財産として管理している信託銀行があります。信託銀行は、受託会社と呼ばれます。受託会社は、1つ1つの投資信託の資産(ファンドの信託財産)の口座を、自行のほかの口座と区別し管理しています。これを分別管理といいますが、投資信託の大きな特徴の1つです。
この分別管理によって、投資家の資産である信託財産は、運用会社である委託会社、窓口である販売会社、信託財産を管理している受託銀行、どの会社が破綻した場合でも保全されるのです。投資信託の信託財産は、それだけ独立性の高い資産として運用・管理されているということになります。
そして、このような投資信託の運営にはコストがかかりますので、投資家はその一部を負担することになります。
投資信託のおもなコスト

それでは、投資信託のコストについて、どのようなものがあるか見ていきましょう。投資信託のコストには、いくつかの種類があります。購入時にかかるコスト、保有期間中にかかるコスト、換金時にかかるコストと、大まかにいえばこの3つの段階でコストがかかってきます。
購入時にかかるコスト
まず購入時には、「購入時手数料」がかかります。最近は、この購入時手数料がはじめからゼロの投資信託(ノーロード・ファンド)もあります。この購入時手数料は、販売会社が独自に料率を決定することが多いので、同じ投資信託でも、販売会社が異なると購入時手数料の料率が異なっていることもあります。
購入時手数料を受け取る会社は販売会社であり、運用会社(委託会社)や信託銀行(受託会社)には、無関係のコストとなります。
保有期間中にかかるコスト
次に投資信託の保有期間中にかかるコストですが、おもなものは、交付目論見書で「運用管理費用(信託報酬)」として説明されているものです。
「信託報酬」という用語は法律用語ですが、「運用管理費用」という用語は法律には登場しません。この用語(運用管理費用)は、投資信託に関する用語をよりわかりやすい表記に見直すことになり、投資信託協会において検討され採用されたものです。
確かに投資家が負担するコストが"報酬"という表記ではわかりにくいといえるかもしれません。「費用」と表記したほうが、読み手である投資家にとってはしっくりくるでしょう(本稿では、「信託報酬」と表記します)。
保有期間中には信託報酬のほかにも、いろいろとコストがかかっています。それらは、従来、限定的で負担もさほど大きなものではありませんでした。しかし、最近は少し事情が異なってきています。これについては、のちほど説明します。
換金時にかかるコスト
そして換金時にかかってくるコストとして、「信託財産留保額」があります。これはその名の通り、信託財産に留保される費用、つまり信託財産に残していくお金のことになります。換金する際に、解約代金の一部を信託財産に残していく、というイメージです。
信託財産留保額は、すべてのファンドにあるわけではありません。どういうケースかというと、投資家がファンドを換金する際には、ファンドにある有価証券等を現金化して投資家に返す必要がありますが、その際、通常より高いコストを支払う必要のある資産を組入れている場合があります。そういったファンドには、信託財産留保額が設定されています。
これは換金する投資家がコストを支払わず、継続保有する投資家がコストを支払うことになるという、矛盾を解消し、投資家間の公平を期すためのコストといえます。この信託財産留保額は、残った投資家の信託財産に組み込まれることになります。
販売会社、運用会社(委託会社)、信託銀行(受託会社)が受け取るコストではない、という点にご留意ください。
信託報酬の内容は?

投資信託は、はじめに書いたように、販売会社、運用会社(委託会社)、信託銀行(受託会社)という3つの会社がその運営にたずさわっています。そして信託報酬は、ファンドの信託財産から、まずは運用会社(委託会社)に支払われたのち、その一部が販売会社と信託銀行(受託会社)に定められた料率に従って支払われます。
投資信託協会の「交付目論見書の作成に関する規則に関する細則」では、交付目論見書への記載事項が詳しく定められています。その中で、信託報酬は「支払先毎に(略)、以下の事項を参考に対比できるよう表内に記載するものとする」とされています。
(委託会社)
委託した資金の運用の対価
(販売会社)
運用報告書等各種書類の送付、
口座内でのファンドの管理、
購入後の情報提供等の対価
(受託会社)
運用財産の管理、
委託会社からの指図の実行の対価
(「交付目論見書の作成に関する規則に関する細則」より引用)
これは、信託報酬が各会社の"何の役務"に対し支払われるかを説明しているものです。
これを参考にして、「交付目論見書」を作成する各運用会社(委託会社)は、表現に工夫をこらしています。このうち運用会社(委託会社)の部分については、より詳しく書かれているものもあります。たとえば、次のような説明内容です。
【ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等】
このように記載している運用会社(委託会社)も多いので参考にしてください。この表記内容は、このあとの「その他の費用」と関連してきます。
「その他の費用」について
投資信託の保有期間中は「信託報酬」のほか、株式の売買委託手数料や信託事務に関する費用などが「その他の費用」として計上されます。
この「その他の費用」について、最近は少し内容が変化してきているので、注意して見てほしいと思います。というのは、運用会社(委託会社)の役務の内容とコストの関係が、会社によって異なってきているからです。
先ほどの例では【ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等】と記載している通り、この会社ではこのような委託会社の役務の対価をすべて信託報酬で賄っていることになります。
一方で最近は、このうち「法定書面等の作成、基準価額の算出等」の部分を抜き出して、この「その他の費用」において、別途投資家の負担としている運用会社(委託会社)があるのです。
もともとは運用会社(委託会社)が信託報酬の中から賄っていたコストですが、運用会社(委託会社)の中には上限の料率を設けつつも、「その他の費用」として別途、投資家の負担にしている会社もあるということは覚えておいてもよいと思います。
信託報酬はいつ支払うのか
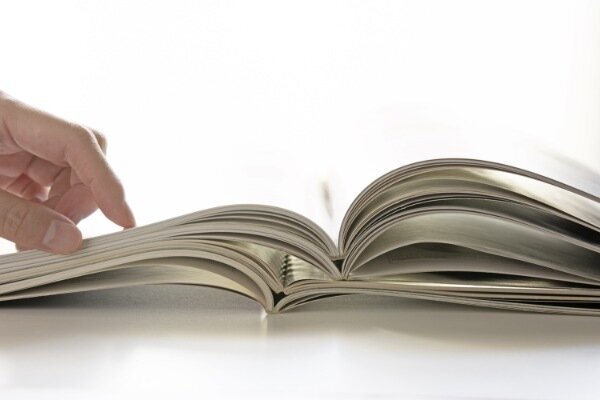
投資信託のコストの中でとても重要な信託報酬ですが、投資家はどのタイミングで支払っているのでしょうか。その答えも、「交付目論見書」の、「信託報酬」の説明の中に記載されています。
先ほど引用した、投資信託協会の「交付目論見書の作成に関する規則に関する細則」には、「運用管理費用(信託報酬)については、運用管理費用(信託報酬)の総額表示のみでなく、支払先毎にその算出方法、金額又は料率、徴収方法及び徴収時期を記載する」と規定されています。
これを受けて、各運用会社(委託会社)は、「信託報酬」の徴収方法および徴収時期を記載しています。記載例としては、たとえば、次のようなものが一般的です。
「信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。」(野村アセットマネジメント「野村インデックスファンド・日経225」)
このように、信託報酬は日々計上されています。つまり、毎日計算され、基準価額を計算する際に、投資家の資産である信託財産から控除されている、ということになります。
交付目論見書をしっかりと確認しよう
「交付目論見書」はカラフルなものも多くなり、以前より親しみやすくなったと感じます。ただ、「ファンドの費用」のページは活字だらけで、しかも投資信託特有の専門用語が多く、依然として読みづらい部分かと思います。
このページは、とかく数値を見るだけで済ませてしまいがちですが、ご自身の財産から負担しているコストですので、しっかり内容を確認していただけたらと思います。
信託報酬などコストだけで投資信託を見てしまうと失敗する?!
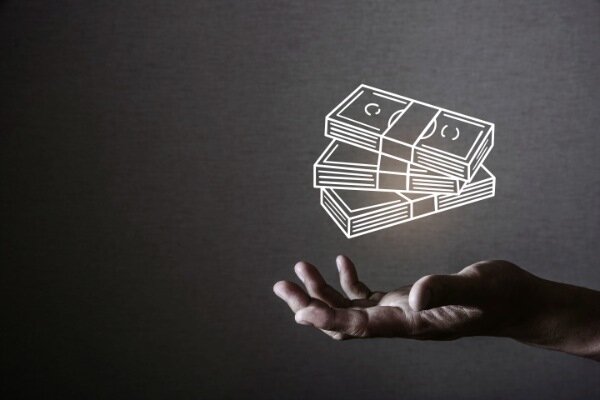
信託報酬は、投資信託を運営していく上で必要なコストを賄うものです。では、この信託報酬の高低を基準に投資信託を選んでいいのか、というとそうではありません。
なぜかというと、投資信託はその運用方針に沿って運用される金融商品なので、運用方針がまったく違うファンドの信託報酬を比較して良し悪しを判断すべきではないからです。もし単純に、信託報酬が低い投資信託は良くて、信託報酬の高い投資信託は劣っているとするならば、それは誤った理解といえます。
信託報酬を比較する前にまず何を確認する必要があるのか。それは、投資信託の「商品分類」や「属性区分」といわれる投資信託の種類でしょう。そして、同じ種類の投資信託同士について、長期の運用成果を比較して判断すべきだと考えられます。
ただし、信託報酬の高低で、投資信託を選んでいい場合もあります。それは、一定の株価指数などに連動することを目的としているインデックスファンドと呼ばれる投資信託です。
株価指数への連動を目的として運用された(信託財産から控除される信託報酬が低い)投資信託のほうが、連動率が高くなることは当然のことになります。一定の株価指数などへの連動率を高めることが目的のインデックスファンドでは、信託報酬の低いファンドのほうが望ましいといわれるのはこういう理由からです。
重視すべきは運用のパフォーマンス
指数連動型のインデックスファンド以外にも、数多くの投資信託が存在します。インデックスファンドと呼ばれるファンドは、投資信託協会の統計によれば、2021年1月末で、公募株式投資信託5,815本中、1,014本です。インデックスファンド以外にも4,800本近くの投資信託があるということになります。
この約4,800本には、いろいろな種類の投資信託が含まれていますので、運用パフォーマンスで比較するといっても、単純に一律に比較しても、これも意味あるものとはいえません。
たとえば、中国の株式に投資する投資信託と、先進国の債券に投資する投資信託を比較しても、どちらが良いファンドかということを判断するには、あまり意味がないということはおわかりいただけると思います。
ですから、投資信託を運用パフォーマンスで比較する際は、できるだけ同じ投資対象、同じ投資地域、このあと説明する同じ運用スタイルなどでまとめた上で比較したほうが、意味のあるものになるでしょう。
投資信託のタイプと信託報酬の関係

投資信託の運用スタイルを大きく分けると、アクティブファンドとパッシブファンドに分かれます。アクティブファンドにもいくつかの運用スタイルがあるのですが、今回は割愛させていただきます。
アクティブファンドは、ベンチマークと呼ばれる指標(運用成績を測るモノサシというべきもので、「運用実績を評価・測定するための基準となる指標のこと」(投資信託協会HP 用語集))に対して、それを上回る運用成果をめざすファンドです。ファンド・マネージャーと呼ばれる運用の専門家が、積極的に、投資対象、組入比率、売買のタイミングなどの投資判断を行いながら運用するファンドです。
一方、パッシブファンドは、ベンチマークに連動する運用成果をめざすファンドです。東証株価指数(TOPIX)や日経平均株価(日経225)といった各種指数と同じ運用成果をめざすインデックスファンドがその代表例です。
一般的に、信託報酬の水準は、アクティブファンドが高く、パッシブファンドが低い傾向にあります。それは、アクティブファンドの場合、投資対象地域や個別の銘柄などの調査・分析をするのにコストがかかることがおもな理由とされています。
ただ、アクティブファンドの中にも1.00%を下回るような相対的に信託報酬の低いファンドもありますし、パッシブファンドの中にも信託報酬が0.50%を上回るファンドも見られますので、やはり個々のファンドの「交付目論見書」でしっかり確認しましょう。
投資信託の投資対象による信託報酬の違い
さまざまな事情から、個々のファンドによって信託報酬の水準は異なっています。先ほど説明した、運用スタイルもその1つです。
それとは別に、株式と債券を比較した場合、一般的にはおもに債券に投資するファンドのほうが、株式に投資するファンドに比べ、信託報酬は低くなる傾向があります。
現在は、先進国の多くで金利水準が非常に低い状況にあります。こういう環境下では、「利息収益などで利回りを確保する」という債券ファンドの商品性を維持するために、信託報酬の水準を低くすることが一般的です。
また、国内への投資を主とするファンドと、海外の株式や債券に投資するファンドを比較すると、一般的には、海外の株式や債券に投資するファンドのほうが、信託報酬は高くなる傾向にあります。
これは、比較的リスクの高い資産や地域に投資する場合と、比較的リスクの低いものに投資する場合とでは、期待できるリターンの大きさも異なってくるため、信託報酬はそういうことも考慮して決定されるからということもできるでしょう。
つみたてNISAの信託報酬はどのくらい?

購入時手数料や信託報酬などコストの面において利用を検討したいのが、税制優遇がある「つみたてNISA」です。つみたてNISAとは何か、既にご存知の方も多いと思いますが、もう一度確認しておきましょう。
つみたてNISAとは
NISAとは、2014年1月にスタートした、少額から投資を行う人のための非課税制度で、「少額投資非課税制度」と呼ばれます。英国のISA(Individual Savings Accountの略)をモデルにして設けられた日本の税制優遇制度です。英国のISAに日本(Nippon)を付けてNISAと呼んでいます。NISAには、一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAの3つの制度があります。
この制度の何がおトクなのかというと、「通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して約20%の税金がかかります。NISAは、「NISA口座(非課税口座)」内で、毎年一定金額の範囲内で購入したこれらの金融商品から得られる利益が非課税になる、つまり、税金がかからなくなる制度」(金融庁「NISA特設ウェブサイト」より)ということなのです。
そして、つみたてNISAは、「特に少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です(2018年1月からスタート)。購入できる金額は年間40万円まで、購入方法は累積投資契約に基づく買付けに限られており、非課税期間は20年間であるほか、購入可能な商品は、長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られています」(金融庁「NISA特設ウェブサイト」より)という制度です。
なお、現在は口座開設可能期間が2037年までとなっていますが、これは2042年まで延びることが決まっています。
つみたてNISAのコストについて
前述したように、つみたてNISAで購入可能な商品は、金融庁の定める一定の要件を満たした投資信託に限定されています。2020年12月23日現在、インデックスファンド167本、アクティブファンド等19本、ETF7本となっています。
一定の要件としては、信託期間が無期限あるいは20年以上、毎月分配ではないこと、などの共通要件のほか、コストなどについてもファンドタイプごとに上限が定められています。インデックスファンドとアクティブファンド等についてみてみると、次のようになっています。
インデックスファンドは
- ノーロード(購入時手数料が無料)
- 信託報酬は、国内資産の場合、0.5%以下(税抜)、海外資産の場合、0.75%以下(税抜)
- ノーロード(購入時手数料が無料)
- 信託報酬は、国内資産の場合、1.0%以下(税抜)、海外資産の場合、1.50%以下(税抜)
コストに関する要件は、公募の投資信託全般と比較しても低い水準に抑えられていますし、何と言っても売却益や配当・利息に対する税金が非課税となる、とてもおトクな制度です。国が、国民の資産形成を後押しするべく創設した非課税制度ですので、これを使わない手はないでしょう。
商品の仕組みやコストをしっかり理解しよう
投資信託をはじめるにあたっては、商品の仕組みやコストをしっかりと理解することが大切です。投資の目的や自身のリスク許容度(投資信託の価格変動に耐えられる度合い、言い換えると、収益がどの程度のマイナスまでなら耐えられるか)も踏まえ、今後の資産形成にお役立ていただければと思います。
執筆者:大地恒一郎
株式会社アセットデザインラボ代表
AFP、2級FP技能士、証券アナリスト(CMA)、証券外務員、1級DCプランナー他。
※記事内の情報は更新時点のものです。最新情報は別途ホームページ等でご確認ください。


